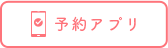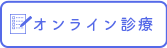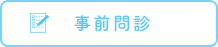ご心配でしたら、まずは気軽にお近くの耳鼻科へ受診してください。
あなたの耳鳴り探索のページへようこそ、あなたの耳鳴り解決へのヒントをご紹介します。
まず、ご自身に向かって確認してみてください。
耳鳴りについて

耳鳴り=病気ではなく、耳鳴=生理的身体感覚のひとつ
耳鳴りがあることは病気。まず、この大きな誤解を解かねばなりません。私自身は、これまで多くの耳鳴を経験してきましたし、現在も経験しています。しかし、それを病気だとは考えていません。
ちょうど皆さんが、今日は肩が凝っているとか、食欲がないといった、様々な生理的なからだの感覚を感じているように、耳鳴は、単なるからだの現状を示す生理的感覚の一つなのです。
もちろん、肩こりや⾷欲低下も、時には何らかの病気の初期症状であったりするように、⽿鳴もそうした場合もあるのは事実です。でも、ほとんどの⽿鳴りは病気ではないのです。とはいえ、自己診断は禁物です。聴⼒検査を経て、難聴の有無と程度の確認といった正確な診断が必要です。実際、耳鳴を主訴に来院された患者さんの中に、他院では異常なしといわれた方でも、多くの耳管開放症の患者さんが発見されています。